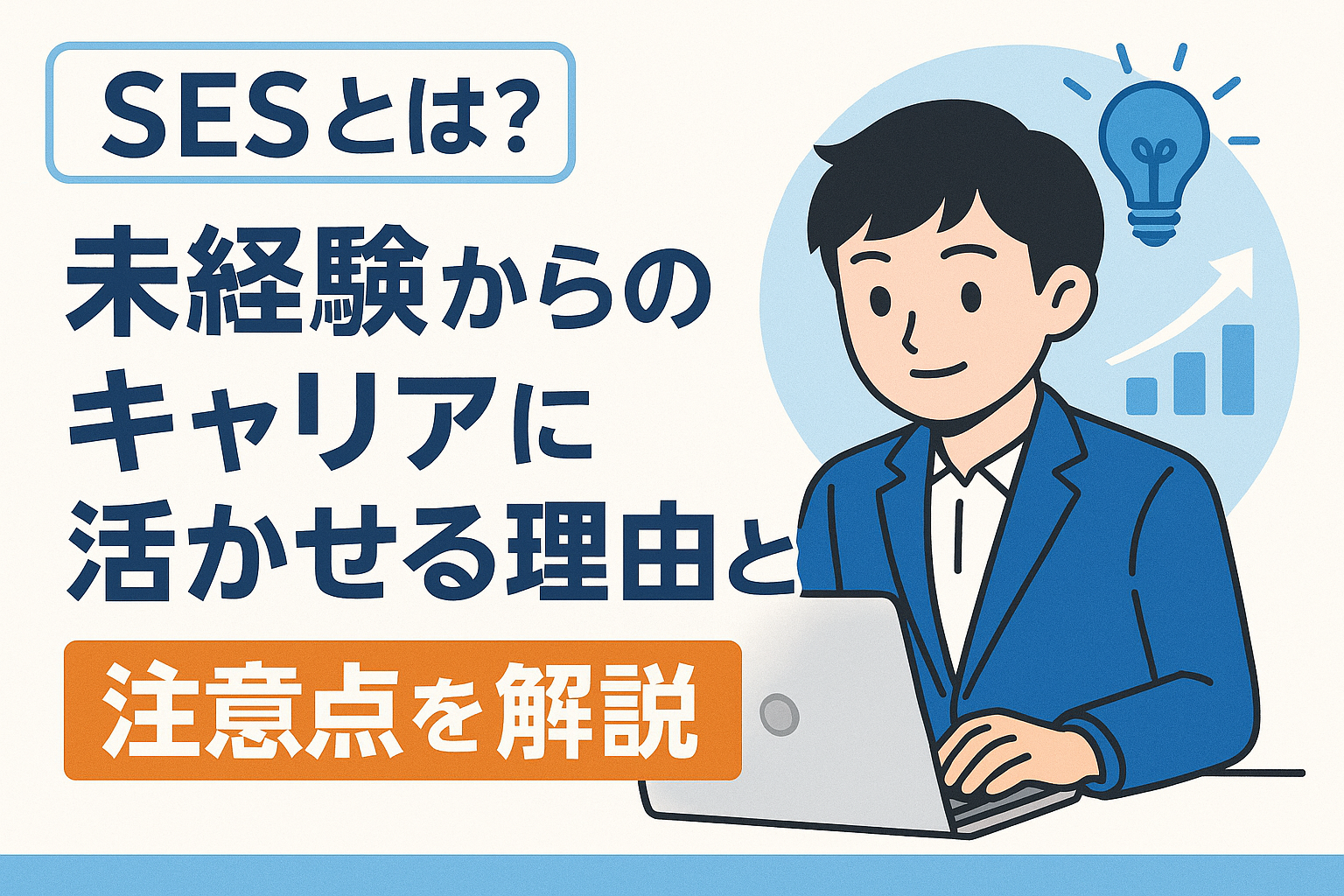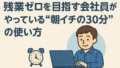「IT業界に興味はあるけど、何から始めればいいかわからない」
そんな方にとって、最初の選択肢となることが多いのが「SES」という働き方です。
SES(システムエンジニアリングサービス)は、エンジニアとして企業に常駐し、クライアントのプロジェクトをサポートする働き方の一種。特に未経験者や異業種からの転職希望者にとっては、現場で実務経験を積みながらスキルアップを目指せる“入り口”として注目されています。
一方で、「SESはやめとけ」といったネガティブな評判が目立つのも事実。実際のところ、SESにはメリットもあれば、注意すべき点もあるというのが本音です。
この記事では、SESとはどんな働き方なのか、なぜ未経験者に向いているのか、そして働くうえで知っておきたい注意点までを丁寧に解説していきます。
IT業界での第一歩を迷っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
SESとは?仕組みと業界での位置づけ
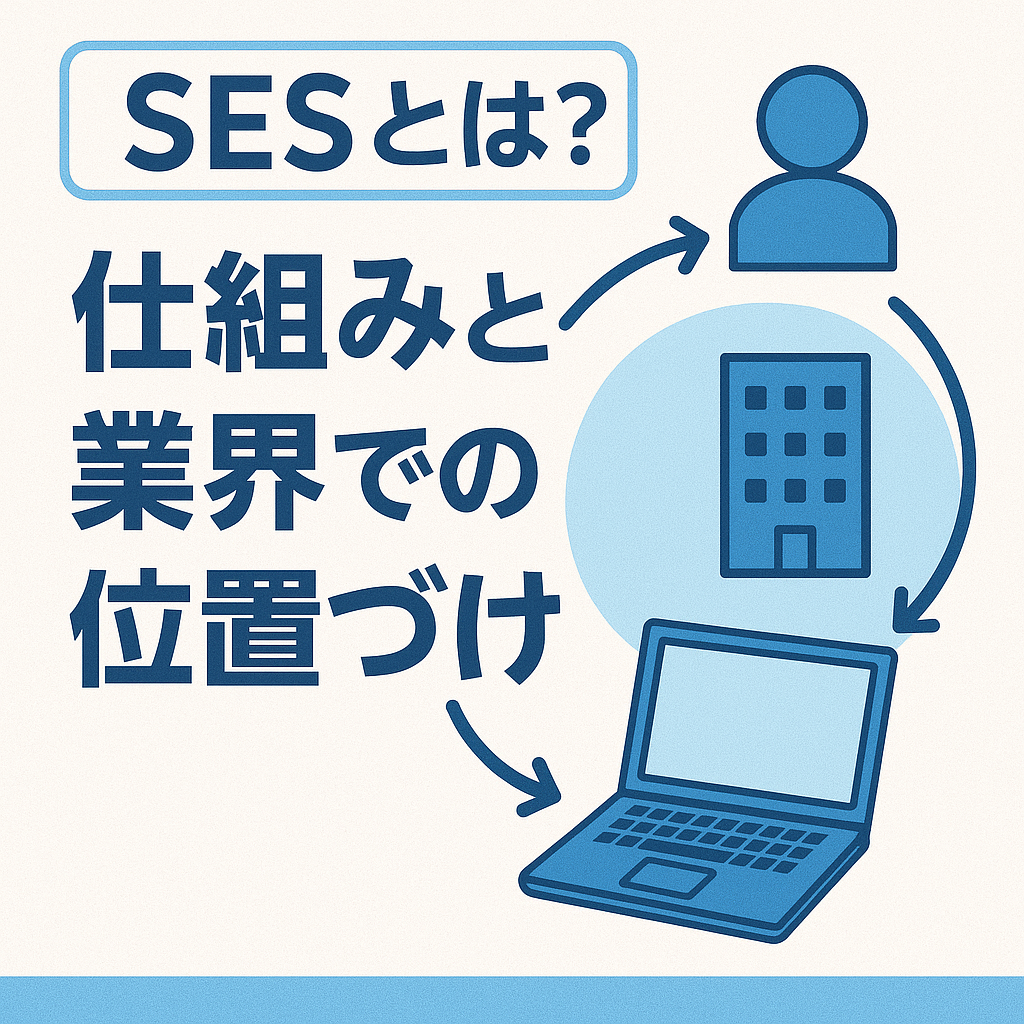
SESは「システムエンジニアリングサービス(System Engineering Service)」の略称で、エンジニアがクライアント企業に常駐し、技術的な支援を行う働き方を指します。IT業界では人手不足が深刻な中、即戦力となる人材を柔軟に確保する手段として広く活用されています。
SESは未経験者でもIT業界に入りやすい仕組みである一方、ほかの契約形態とは明確な違いがあるため、まずはその構造を正しく理解することが重要です。
SESの基本構造:三者間の関係性
SESでは、エンジニア(労働者)、SES企業(所属元)、クライアント企業(常駐先)の三者間で契約が成立しています。
- エンジニアはSES企業に所属しながら、クライアント企業の現場で業務を行います。
- クライアントとSES企業の間には「準委任契約」が結ばれ、業務に対して支援を行う契約となります。
- 指揮命令権はSES企業側にあり、派遣契約とは異なる点がポイントです。
つまり、エンジニアが常駐先で働いていても、業務上の管理責任や評価は自社が持ちます。
SESと他の契約形態との違い
SESは「派遣」や「請負」と混同されがちですが、契約の目的や責任の所在が異なります。
| 契約形態 | 契約の対象 | 指揮命令権 | 成果責任 |
|---|---|---|---|
| SES | 業務支援 | SES企業 | なし |
| 派遣 | 労働力 | 派遣先企業 | なし |
| 請負 | 成果物 | 請負元企業 | あり |
SESは「成果」ではなく「業務の遂行」が目的となっており、納期や品質の責任は発生しません。そのため、比較的プレッシャーの少ない形で実務経験を積むことができます。
IT業界におけるSESの役割
現在、IT業界では案件数が急増している一方で、慢性的な人材不足が続いています。とくにスタートアップや中小企業では、即戦力の人材を採用する余裕がない場合も多く、SESを活用してプロジェクトを回すケースが増えています。
また、エンジニア側にとっても、「実務経験を積める場」としてSESは価値があり、未経験者が最初に踏み出すフィールドとして注目されています。
このように、SESはIT業界において人材と現場をつなぐ柔軟な働き方のひとつです。正しく仕組みを理解すれば、自身のキャリアを築くうえで有効な選択肢となり得ます。
SESの仕事内容と求められるスキル
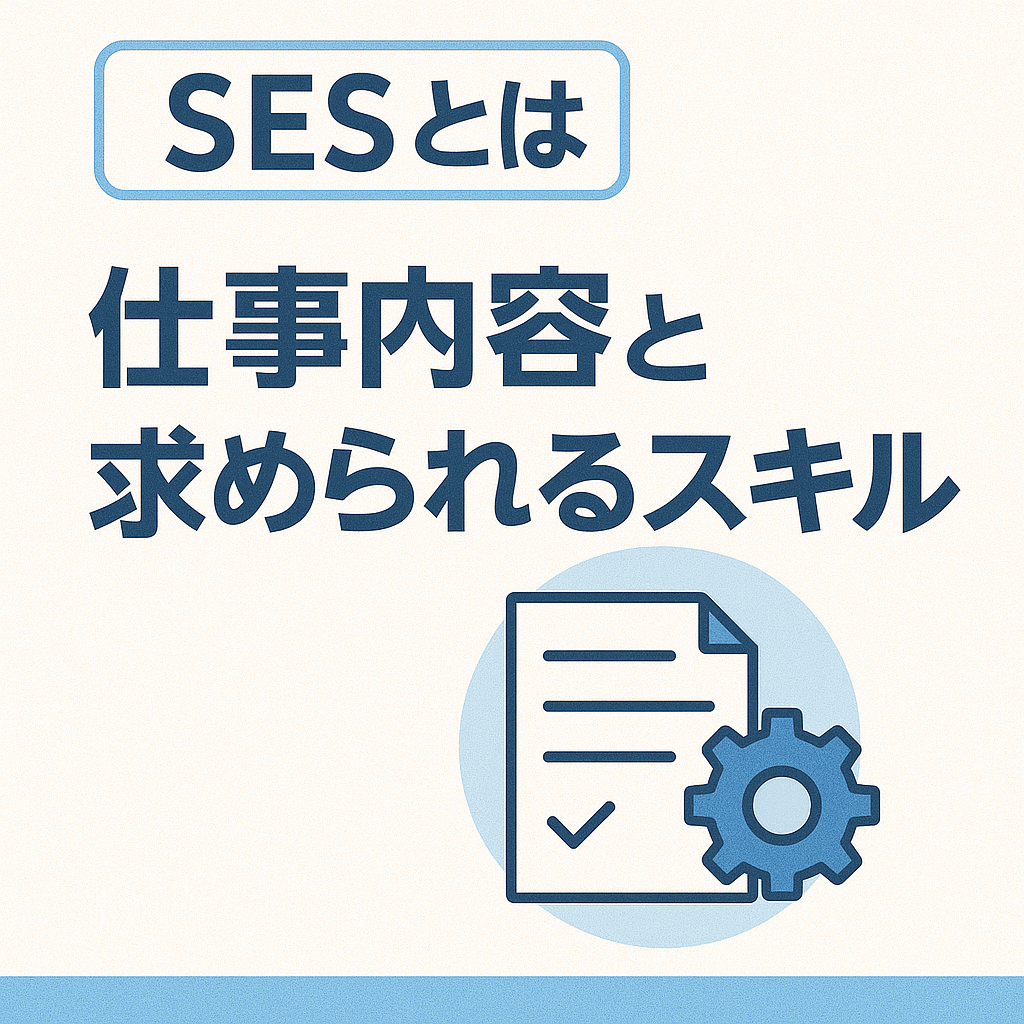
SES(システムエンジニアリングサービス)で働くエンジニアの仕事は、配属される案件によって大きく異なります。
開発現場でのコーディングから、インフラの運用保守、テスト作業、ヘルプデスクまで、多種多様な業務があります。
未経験者にとってもチャレンジしやすい反面、どのような現場でどのようなスキルが求められるのかを事前に知っておくことが大切です。
よくあるSESの業務内容
SESとして参画する業務は、以下のようなカテゴリに分類されます。
- 開発業務:システムやアプリの設計・開発・テストなど
- 運用・保守:既存システムの監視、障害対応、パフォーマンス改善など
- インフラ構築:サーバーやネットワークの構築・管理
- テスト工程:仕様に基づいた動作確認やバグ報告
- サポート業務:ヘルプデスクやユーザー対応など
案件の難易度も幅広く、未経験から始められるテスト業務やサポート業務も多く存在します。
働き方の特徴:常駐スタイルとその実態
SESの特徴として、「クライアント先への常駐勤務」があります。これは、自社ではなくクライアント企業のオフィスで勤務し、現場のチームとともに作業を行うスタイルです。
常駐先では、以下のような特徴があります:
- 日常的なコミュニケーションは常駐先の担当者と行う
- 案件によっては複数社のSESエンジニアが混在していることも
- クライアントの文化やルールに柔軟に対応する姿勢が求められる
自社とのつながりが薄く感じることもありますが、企業によっては定期的な面談やフォロー体制を整えており、メンタルケアやキャリア支援が行われています。
SESで求められるスキルと姿勢
SESとして活躍するためには、技術力だけでなく、現場に馴染むためのヒューマンスキルも重要です。
| スキル・姿勢 | 説明 |
|---|---|
| 基本的なITリテラシー | OSやネットワーク、Officeソフトの理解など |
| コミュニケーション力 | 現場の人と円滑に連携する能力 |
| 柔軟性と適応力 | ルールや進め方が案件ごとに異なるため必要 |
| 継続的な学習姿勢 | スキルアップが昇給・案件幅の拡大につながる |
特に未経験の場合、「学ぶ姿勢と現場での振る舞い」が評価されやすいため、技術以上に人柄が重視されることもあります。
SESは、多様な現場を経験できるぶん、自分の適性を見極めるチャンスでもあります。今のスキルに自信がなくても、意欲と行動力があれば十分に成長できるフィールドです。
未経験からSESをキャリアの足がかりにする理由
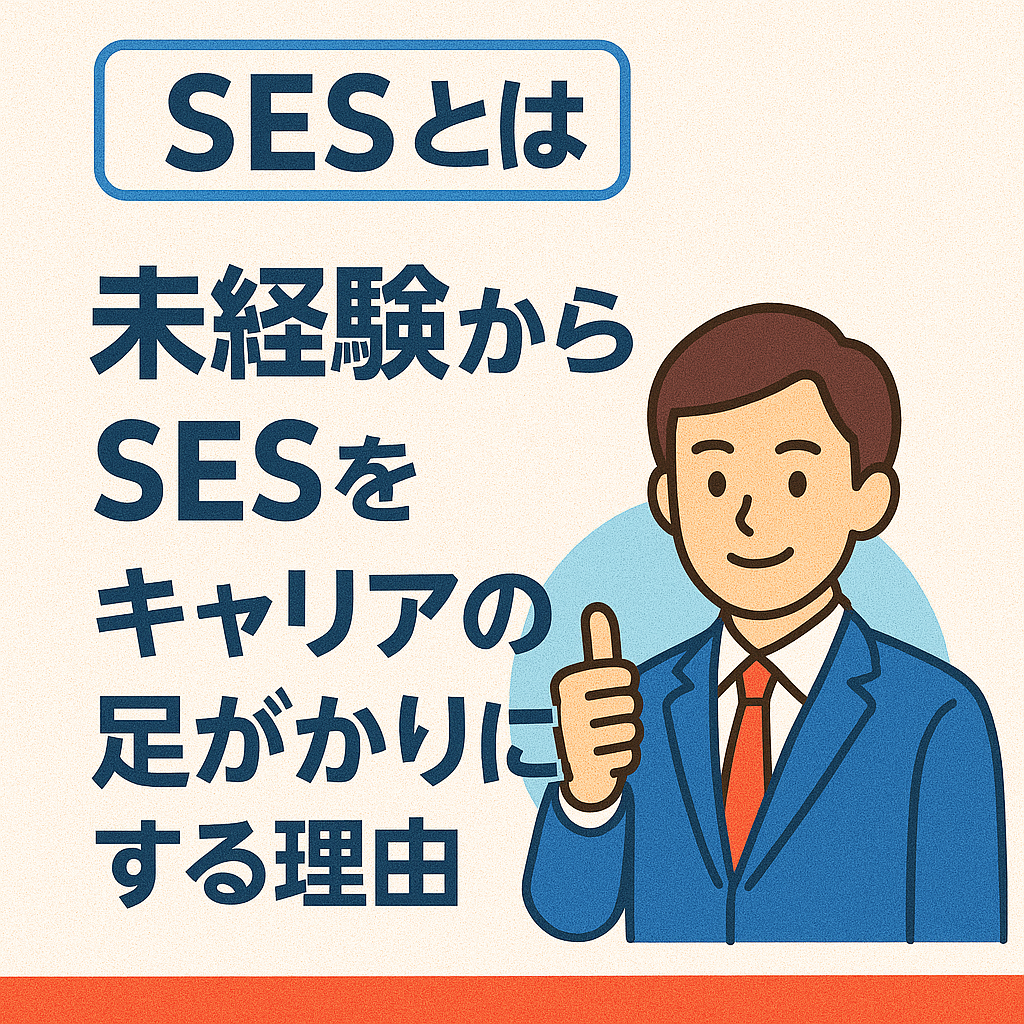
IT業界は成長が著しい一方で、常にエンジニア不足が課題となっています。
その中でもSESは未経験者を受け入れる間口が広く、実務を通じて成長できる環境として注目されています。
ここでは、なぜ未経験者にとってSESがキャリアの第一歩になり得るのか、その理由を具体的に見ていきましょう。
未経験歓迎の求人が多い
SES企業の多くは、未経験者でも応募可能な案件を多数抱えています。
その背景には以下のような事情があります:
- クライアントから「育成前提」での依頼を受けている場合がある
- シンプルなテスト業務やサポート業務など、難易度の低い工程も存在する
- IT業界の人材不足が深刻で、ポテンシャル採用が重視されている
そのため、他業種からのキャリアチェンジでも比較的挑戦しやすいのが特徴です。
現場での経験がスキルに直結する
SESの最大の強みは、「実際の開発・運用現場で働けること」です。
現場では以下のような経験が積めます:
- 現場で使用されている実践的なツールやフレームワークへの理解
- チーム開発やアジャイル運用など、現場特有の進め方への対応力
- 問題発見・報告・改善といったビジネススキル
これらは書籍やスクールでは得にくい“現場力”であり、次のステップに進むための大きな武器になります。
キャリアの選択肢が広がる
SESで一定の経験を積んだ後は、以下のようなキャリアパスが考えられます:
- より高度な案件へのチャレンジ(設計・上流工程など)
- 自社開発企業への転職
- フリーランスとして独立
- ITコンサルタントやPM(プロジェクトマネージャー)へのキャリアアップ
つまり、SESは“ゴール”ではなく“通過点”としての価値が高いのです。
未経験だからこそ柔軟に吸収できる
IT業界には独自の文化や考え方があるため、最初のうちは戸惑うことも多いでしょう。
しかし、未経験であることは「先入観なく吸収できる」という強みでもあります。
- 常駐先ごとのルールに素直に対応できる
- 各工程の意味を一つひとつ理解しながら進められる
- 柔軟なマインドでチームに溶け込める
その姿勢は、現場からも高く評価されることが少なくありません。
未経験からIT業界に飛び込むのは不安もありますが、SESは現場で成長しながらキャリアを築ける、実践的な登竜門です。
「経験がないから無理」とあきらめる前に、一歩踏み出してみる価値は十分にあります。
SESで働く上での注意点と課題

SESは未経験からIT業界に挑戦できる入り口として魅力的ですが、働くうえでの注意点や課題もあります。事前にそれらを理解しておくことで、入社後のギャップを減らし、より良いキャリアを築くことができます。
案件ガチャ問題:希望の業務に就けるとは限らない
SESでは、自社が受託している案件の中から空きポジションにアサインされるのが一般的です。そのため、自分の希望とマッチしない業務に配属されることもあります。
- 例:開発を希望していたがテストや運用の案件に配属された
- 長期的に希望外の業務が続くことで、モチベーションが下がることも
案件の選択権がどの程度あるのかは、企業によって大きく異なるため、入社前に確認することが重要です。
教育・成長環境に差がある
SES企業は数が多く、企業ごとの教育制度やサポート体制に大きな差があります。
- 独学が前提の企業もあれば、充実した研修・OJTを提供している企業も
- アサイン後のフォローが手薄なケースでは、孤独感や成長の停滞につながることも
未経験から入る場合、成長を支える仕組みがあるかどうかは非常に大切なポイントです。
帰属意識の薄れと孤立感
SESエンジニアはクライアント先で働くため、自社の同僚と顔を合わせる機会が少ない傾向にあります。
- 孤立感を感じやすく、社内文化になじめないまま退職するケースも
- 昇給や評価の基準が見えづらいと、不安を感じやすい
こうした状況に対して、定期面談やチャットサポートなど、社内との接点を大切にしている企業かどうかを見極めることが大切です。
キャリア設計は自分次第
SESでは、業務の幅を自分で広げていく意識が求められます。
常駐先で求められる役割をこなすだけでなく、将来を見据えて以下のような行動が必要になります:
- 空き時間に技術学習を進める
- 資格取得やポートフォリオ作成を通じてスキルの“見える化”を図る
- 数年後に目指すポジションを明確にする
与えられる教育よりも、「自ら学び、成長する姿勢」がその後のキャリアに大きく影響します。
SESは正しく向き合えば大きく成長できる働き方ですが、受け身のままだとスキルが伸びにくい構造でもあることを理解しておきましょう。
「何を目的にSESを選ぶのか」を明確にしたうえで、主体的にキャリアを築いていくことが成功のカギとなります。
良いSES企業を見極めるポイント

SES企業は数多く存在しますが、その質やサポート体制には大きな差があります。
未経験から安心してキャリアをスタートするためには、自分に合った企業を見極める力が非常に重要です。
ここでは、入社前にチェックすべきポイントを具体的にご紹介します。
案件選択の自由度があるか
SESでは、自分がどの案件にアサインされるかによって、その後の成長に大きな影響が出ます。
そのため、以下のような点を確認しましょう:
- 案件内容の希望を伝えられる仕組みがあるか
- 配属前に現場の情報を詳しく共有してもらえるか
- 複数案件の選択肢を提示してくれるか
「配属は会社都合で一方的に決まる」企業は要注意です。
教育制度・フォロー体制が整っているか
未経験からのスタートでは、学習支援や現場でのフォロー体制がどれだけ整っているかがとても重要です。
- 入社時に研修プログラムがあるか
- 常駐後も、定期的な面談やチャットでの相談ができるか
- キャリアアップ支援(資格補助、社内勉強会など)が用意されているか
継続的なサポートがあれば、孤立せずに安心して成長できます。
マージン(手数料)の透明性があるか
SESでは、クライアントから支払われた金額のうち、どれだけがエンジニアに支払われるのか(マージン率)がブラックボックスになっている企業も少なくありません。
- 給与体系や報酬の仕組みを丁寧に説明してくれるか
- マージンや単価の開示があるかどうか
- 昇給の基準が明確に定められているか
金額の透明性は、企業の誠実さを測る一つの指標になります。
キャリアパスを一緒に考えてくれるか
良いSES企業は、エンジニアを「現場に送り出して終わり」にはしません。
その人の将来のビジョンや目標に寄り添ってサポートしてくれる会社こそ、長く付き合うに値する存在です。
- 1年後、3年後にどうなりたいかをヒアリングしてくれる
- スキルや希望に合わせて、案件や研修内容を提案してくれる
- キャリア相談が定期的に実施されている
こうした姿勢が見える会社は、未経験者の不安にも寄り添ってくれる傾向があります。
SESという働き方は企業選びによって、「スキルを伸ばせる場」にも「疲弊するだけの場」にもなり得ます。
「会社がどうサポートしてくれるか」だけでなく、「あなたがどう成長したいか」を軸に、納得のいく選択をすることが大切です。
まとめ:SESは未経験からIT業界に飛び込む第一歩になる
SESは、未経験者がIT業界に入りやすい選択肢として、多くのチャンスを提供してくれます。
現場で実務を経験できるという点においては、非常に実践的かつ成長しやすい環境とも言えるでしょう。
一方で、「どんな案件に配属されるのか」「自分の成長が見込めるか」といった点については、企業ごとに大きな差があります。
SES=誰にでも合う完璧な働き方ではなく、自分の目標やスタイルに合っているかをしっかり見極めることが重要です。
これからSESを検討する方は、以下の点を意識してみてください。
- 将来のキャリア像をざっくりでも描いておくこと
- 教育体制や案件内容などを面談で具体的に確認すること
- 主体的に学び、行動する意識を持つこと
SESはあくまでスタート地点。
うまく活用すれば、数年後には自社開発・フリーランス・上流工程といった幅広いキャリアにつながる道が拓けます。
迷っている方も、「まずは現場で経験を積んでみたい」という想いがあるなら、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。