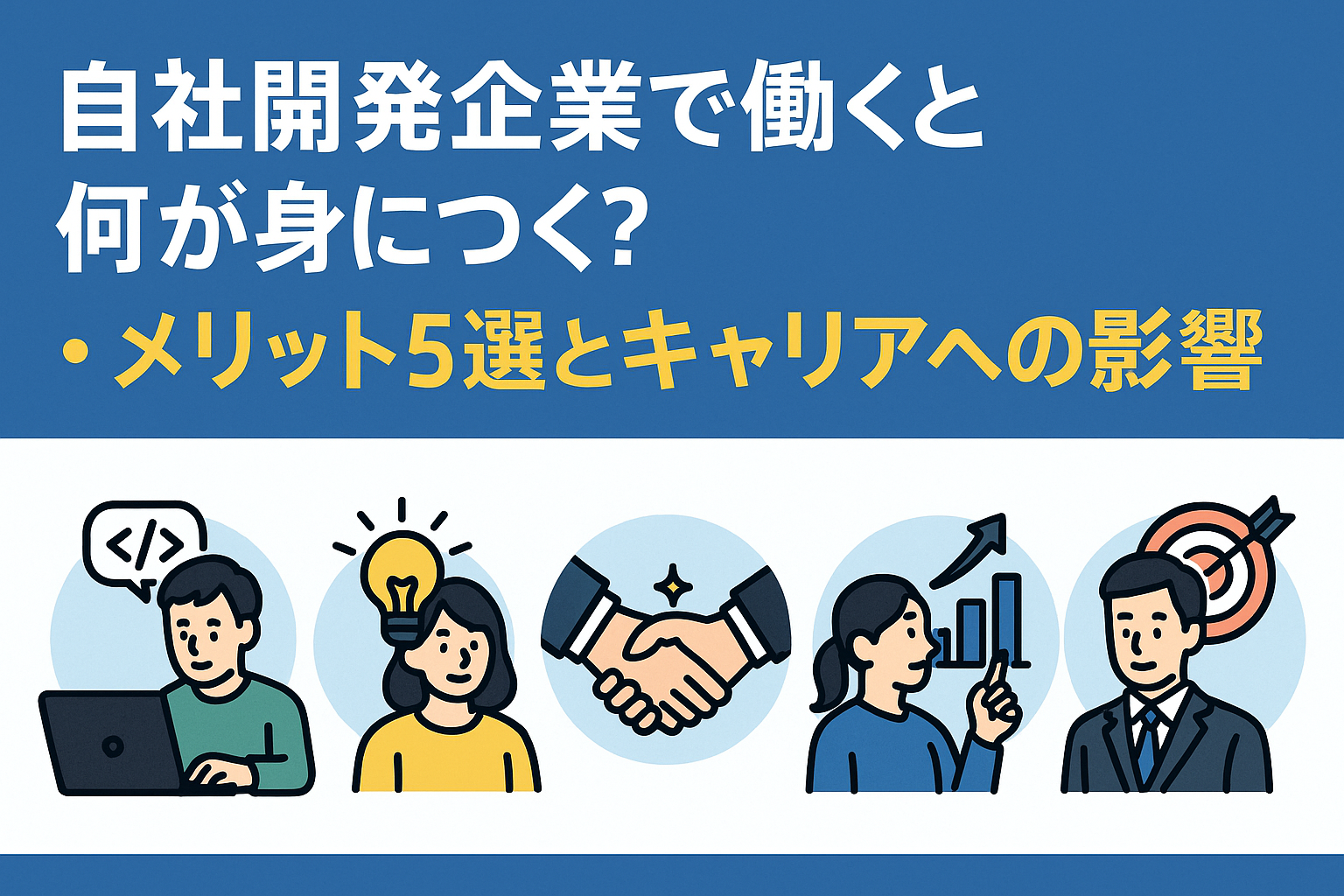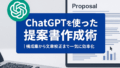「自社開発企業で働くって、実際どんな感じなんだろう?」
IT業界に興味を持ち始めた方や、SES・受託開発との違いがピンとこない方の中には、そんな疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
自社開発企業の魅力は、ただ“自社でサービスをつくっている”というだけではありません。
開発の自由度やチームでの協働、サービスを育てる面白さなど、他の働き方とは一線を画す経験が得られます。
本記事では、「自社開発で働くと何が身につくのか?」を初心者にもわかりやすく解説しながら、メリットを5つにまとめてご紹介します。
さらに、その経験がキャリアにどのように影響するのか、リアルな視点でお伝えしていきます。
自社開発とは?基本をおさえよう
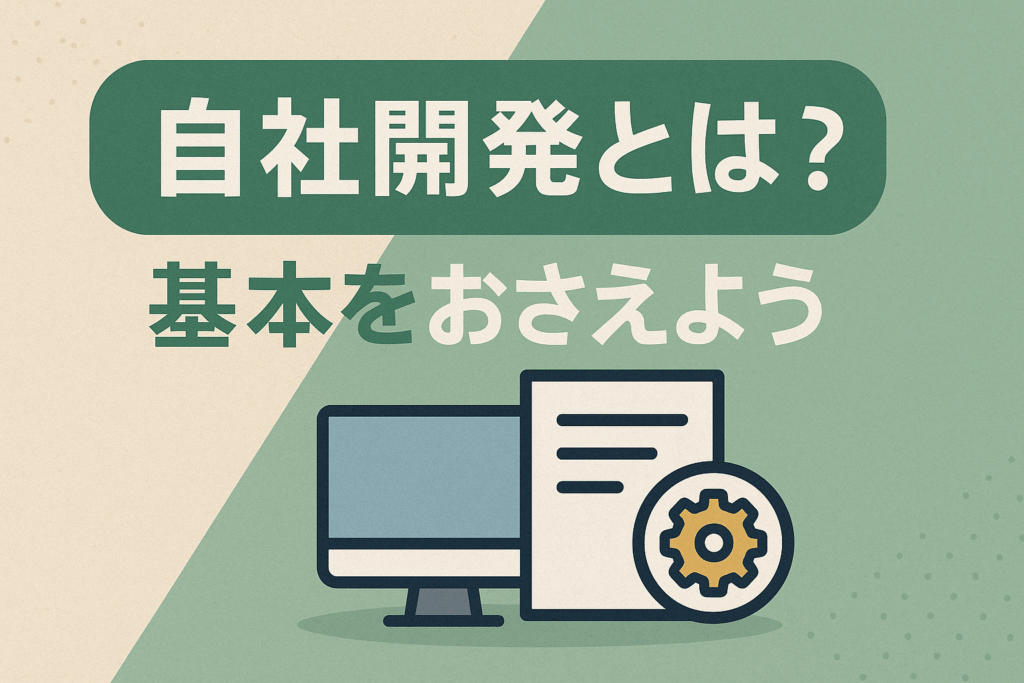
自社開発の定義と特徴
「自社開発」とは、自分たちの会社で企画・開発・運用を一貫して行う開発スタイルを指します。
たとえば、SaaS(クラウド型サービス)やWebアプリ、スマホゲームなど、サービスの企画から実装、リリース、さらには運用・改善までを自社のチームで担う形態です。
自社サービスの成長=会社の成長となるため、開発メンバーがプロダクトに強くコミットできるのも特徴です。
その分、責任も伴いますが、改善提案や新機能のアイデアがすぐに反映される柔軟性は大きな魅力です。
受託・SESとの違いとは?
自社開発とよく比較されるのが、「受託開発」と「SES(システムエンジニアリングサービス)」です。
それぞれの違いをざっくり表にすると、以下のようになります。
| 項目 | 自社開発 | 受託開発 | SES |
|---|---|---|---|
| 主体 | 自社 | クライアント | 出向先(常駐先) |
| 目的 | サービスを自社で育てる | クライアントの要望に応える | 派遣先の業務を遂行する |
| 開発工程 | 企画〜運用まで一貫 | クライアント指示の範囲内 | 担当フェーズに応じる |
| 働き方 | 社内でチーム開発 | 案件ベースで期間限定 | 常駐先での個別対応が中心 |
| キャリア性 | 事業と連動したスキルが育つ | 汎用的な開発経験が得られる | 柔軟性はあるが属人化しやすい |
自社開発は“自分たちのサービスを作る”という視点が根本にあり、プロダクト思考やユーザー視点が養われやすいのがポイントです。
一方、SESや受託では、関わる案件や環境が変わりやすいため、多様な経験を積めるという利点もあります。
自社開発で働くメリット5選
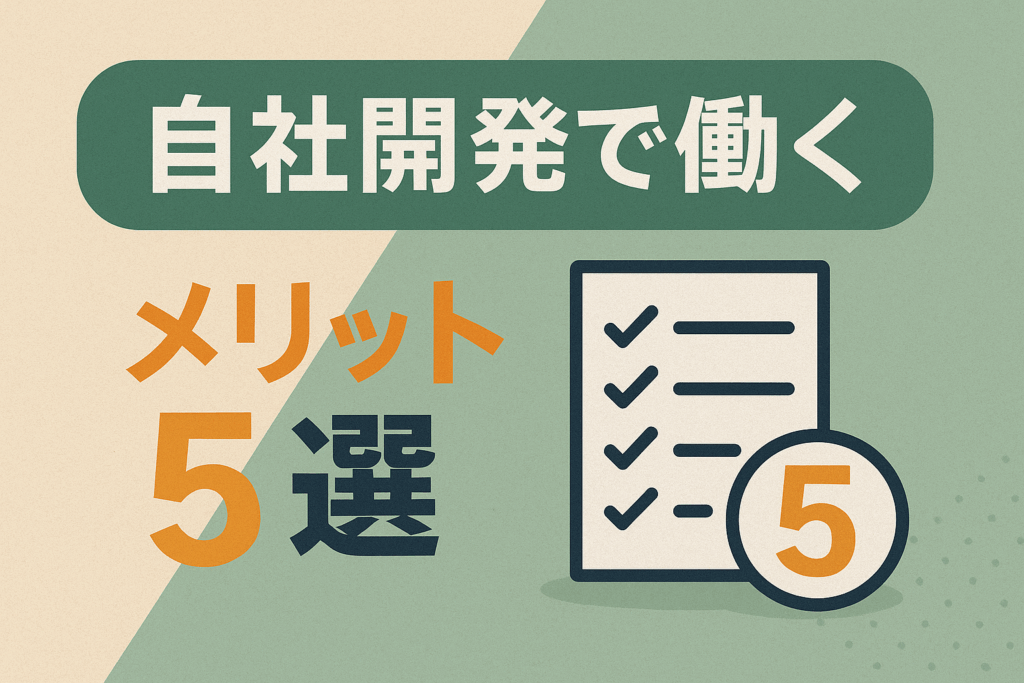
自社開発には、他の開発形態にはない独自のメリットがあります。
ここでは、実際に働いて得られる経験やスキルを5つの観点から具体的に紹介していきます。
① 要件定義から運用まで一貫して携われる
自社開発では、サービスの立ち上げから保守運用まで、開発のすべての工程に関わることができます。
設計・実装だけでなく、ユーザーからのフィードバックを受けて改善する工程まで経験できるため、開発者としての視野が広がります。
「作って終わり」ではなく「作ったあとも育てる」という意識が自然と身につくのが大きな特徴です。
② 技術選定に関われる機会がある
受託開発やSESと異なり、自社開発では使用する言語・フレームワーク・インフラ構成などを自分たちで選定できる場面が多くあります。
もちろんすべて自由に決められるわけではありませんが、技術的な意思決定のプロセスに関われるのは大きなやりがいです。
「なぜこの技術を選ぶのか」といった思考ができるようになれば、開発力に加えて技術的判断力も養われます。
③ ユーザー視点のものづくりができる
自社サービスの成功には、ユーザーに継続的に使ってもらうことが欠かせません。
そのため、ユーザー目線での改善提案やUX設計への関与が求められる機会が多くなります。
開発者でありながら「どうすればもっと便利になるか?」を日々考える習慣が身につくため、ビジネス視点やマーケティング感覚も自然と養われるのが特徴です。
④ チーム開発でリーダーシップが育つ
自社開発では、社内のエンジニアやデザイナー、PdM(プロダクトマネージャー)などと長期的にチームを組んで開発するケースが多くなります。
チーム内での情報共有・進行管理・レビュー文化などが根づいており、自然とリーダーシップやコミュニケーション力が磨かれていきます。
特に、後輩のフォローやプロジェクトの推進役を担う場面では、マネジメント経験の第一歩を踏むことも可能です。
⑤ プロダクトの成長に継続的に関われる
自社開発の最大の魅力のひとつは、同じプロダクトに継続して関われる点です。
サービスが成長する過程を見届けたり、自分の開発した機能がユーザーに使われている姿を実感できるのは、大きな達成感につながります。
「もっとこうしたい」「ユーザーの反応を踏まえて改善しよう」といった改善サイクルに主体的に関われる環境は、やりがいの源でもあります。
キャリアに与える影響と広がる可能性
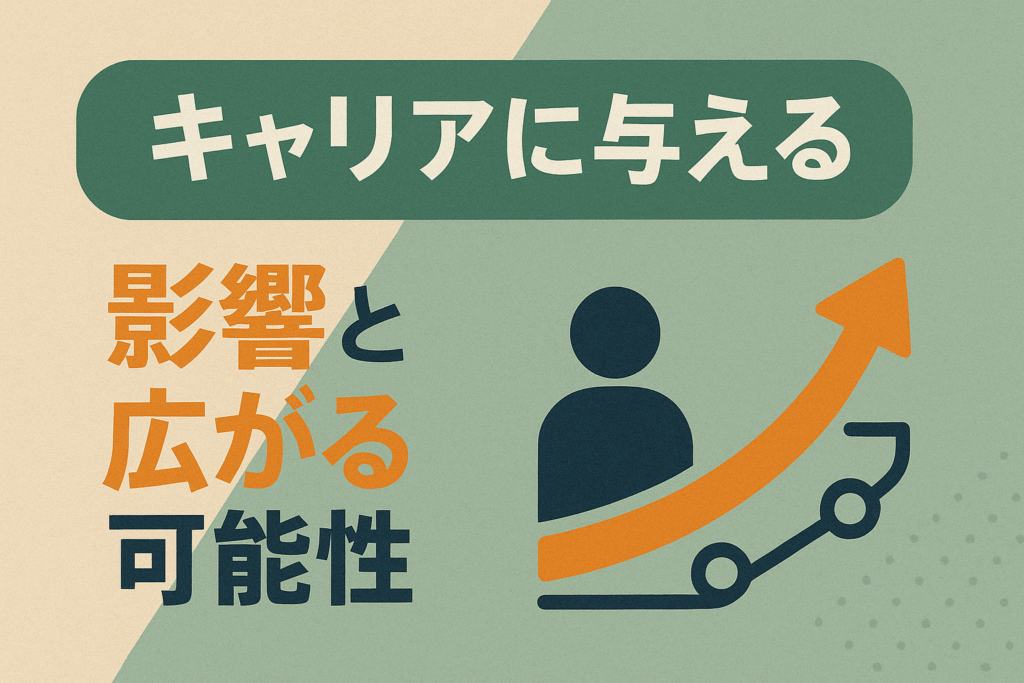
自社開発の現場で培われる経験やスキルは、エンジニアとしての成長だけでなく、将来のキャリア選択肢にも大きく影響します。
ここでは、自社開発で働くことで得られるキャリア面でのメリットに注目して解説します。
PM・PdM・CTOなど上流職への道
自社開発では、プロダクトの設計段階から運用後の改善までを一貫して経験できます。
そのため、単なる「作業者」にとどまらず、企画・戦略に関わるポジションへとステップアップする土台が築かれやすいのが特徴です。
実際、自社開発企業では、PM(プロジェクトマネージャー)やPdM(プロダクトマネージャー)、CTO(技術責任者)などに昇格していく人材が多く見られます。
これは、単なる技術力に加えて、事業視点で動ける人材が重宝されるためです。
サービス全体を見渡せる視野が養われる
受託開発やSESでは「プロジェクトの一部」を担当するケースが多く、サービス全体の構造や運営方針に触れる機会は限られがちです。
一方、自社開発では、常にサービス全体の流れや目的を意識して開発を進める必要があります。
その結果、「この機能がサービス全体でどう位置づけられるのか?」という視野の広い思考が自然と育ちます。
これは将来的に事業開発やプロダクト設計などに関わる上で非常に有利なスキルとなります。
技術力だけでなく“事業理解力”も高まる
自社開発の現場では、技術的なスキルだけでなく「この機能がどうビジネスに貢献するか?」という視点が求められます。
これは、単にコードを書くことにとどまらず、プロダクトの目的やKPI、ユーザー行動まで踏み込んで理解する姿勢を指します。
こうした経験を積むことで、「事業を技術で支える」思考が身につき、他社との差別化につながる人材へと成長できます。
結果的に、将来的な独立やスタートアップ参画にも強い土台となるのです。
自社開発のリアル|やりがいと難しさ
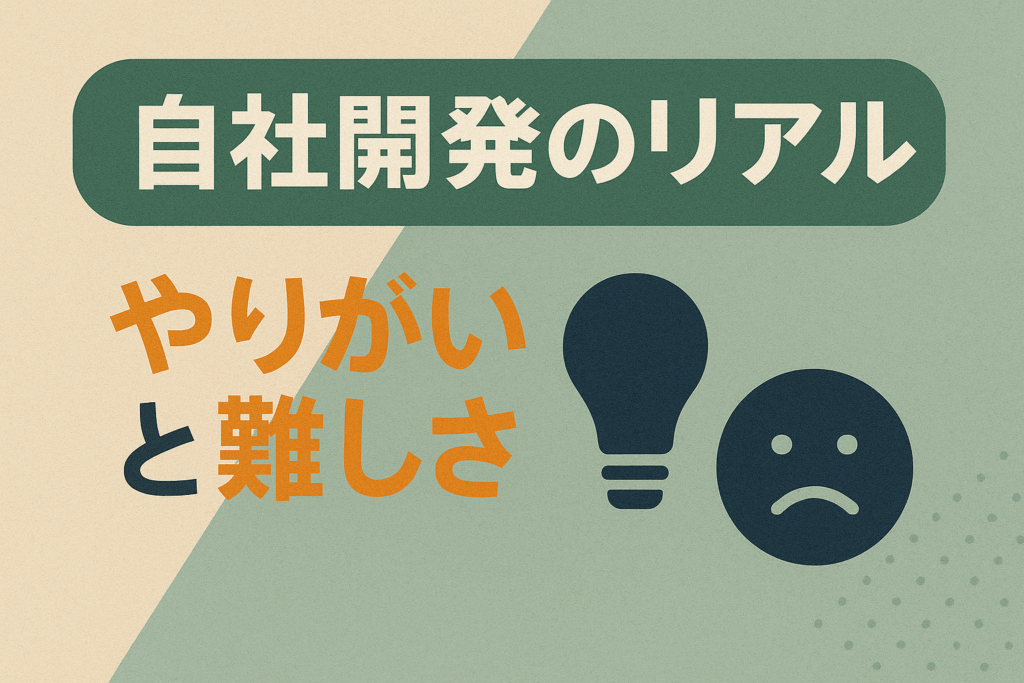
ここまでメリットやキャリアへの影響をお伝えしてきましたが、もちろん自社開発にも大変な面はあります。
このセクションでは、実際に働く中で感じやすいやりがいと、直面しやすい課題の両面を紹介します。
「裁量の大きさ」が生む達成感と責任
自社開発では、比較的自由度の高い環境で開発できるため、自分のアイデアや提案が実装に直結するケースも珍しくありません。
これは非常に大きなやりがいであり、「自分がこのサービスをつくっている」という実感が得やすいです。
一方で、自由と引き換えに責任も重くなるのが現実です。
仕様変更やバグ対応、リリース判断など、チームの中で「任される」瞬間が増えることで、プレッシャーを感じる場面も出てきます。
リリース後の改善・運用のプレッシャー
自社開発の特徴として、「作って終わり」ではなく「作ったあとが始まり」という考え方があります。
ユーザーの反応を見ながらアップデートを重ね、課題を修正し続ける運用フェーズが重要です。
そのため、「どう改善するか?」「本当にこれでいいのか?」という意思決定の繰り返しに頭を悩ませる日々が続くことも。
とはいえ、そうした試行錯誤の中に、“プロダクトを育てる楽しさ”があるのもまた事実です。
事業と一体化するからこその緊張感
自社開発エンジニアは、単に技術者ではなく、事業そのものの一部を担う存在でもあります。
サービスの成長が会社の業績に直結する分、経営視点や数字への意識も求められるケースが少なくありません。
これは裏を返せば、「自分たちの仕事が会社を動かしている」という当事者意識を持って働ける環境とも言えます。
技術職でありながら、ビジネスと地続きのやりがいと緊張感を得られるのは、自社開発ならではです。
まとめ|こんな人におすすめ
ここまで、自社開発の特徴や得られるメリット、キャリアへの影響、そして実際のリアルな側面までご紹介してきました。
では、どんな人が自社開発に向いているのでしょうか?
以下のような思いを持っている方は、自社開発企業で働くことで大きなやりがいと成長機会を得られるはずです。
- 一つのサービスをじっくり育てていきたい人
- 技術だけでなく、企画や改善にも関わってみたい人
- チームで協力しながら働くのが好きな人
- 将来的にPMやPdMなど上流工程も目指したい人
- “作って終わり”ではなく、“作ったあと”にも関わりたい人
一方で、案件ごとに多様な環境を経験したい方や、短期的な業務を好む方は、SESや受託開発のほうが合っているかもしれません。
どの働き方が正解というわけではありません。
大切なのは、自分の価値観やキャリア目標に合った選択をすることです。
この記事が、あなたの働き方を見つける一助になれば幸いです。