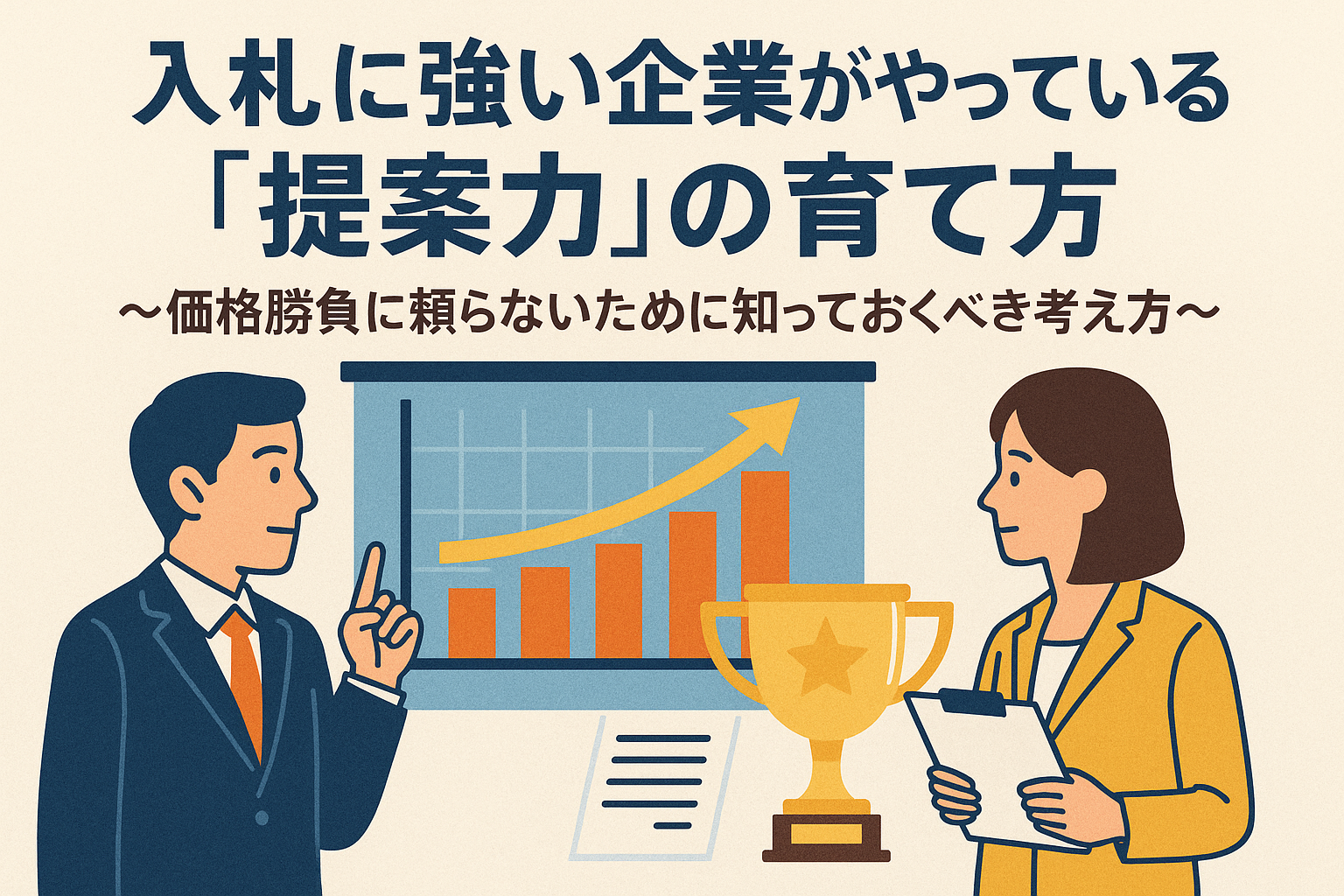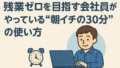「価格は安くしたのに落札できなかった」
「仕様通りに書いたのに評価されない」
そんな悔しい思いをしたことはありませんか?
最近の入札では、単に価格が安いだけでは選ばれなくなってきています。
特に企画提案型の案件やプロポーザル方式の入札では、「いかに魅力的で納得感のある提案を出せるか」が、勝負の分かれ目になります。
つまり今、求められているのは“提案力”という武器です。
提案力とは、ただ体裁よく書く技術ではなく、行政のニーズを的確に捉え、「この会社に任せたい」と思わせる総合力のこと。
本記事では、実際の入札を通して見えてきた“提案で選ばれる企業”の共通点や、提案力を育てるための工夫を、実例を交えてわかりやすく解説します。
「これから入札に挑戦したい」「価格勝負から抜け出したい」と考えている方にとって、ヒントとなる内容をお届けします。
なぜ入札に「提案力」が求められるようになったのか

かつての入札は「いかに安く受けるか」が主な評価基準でした。
しかし近年、特に自治体や公共団体の業務においては、価格だけでなく“提案の中身”が重視される傾向が強まっています。
それはなぜなのでしょうか?
行政側のニーズが「成果重視」にシフトしている
従来は「依頼通りに業務をこなしてくれればOK」という考え方が主流でしたが、
現在は少子高齢化・予算の削減・職員数の減少などを背景に、“より効果的・効率的に成果を出すパートナー”が求められる時代になっています。
たとえば:
- PR動画の制作 → 視聴数や波及効果が問われる
- 地域活性化イベント → 来場者数やSNS露出などの実績が求められる
- サイト運用 → 利便性・更新頻度・アクセス分析なども評価対象に
つまり、仕様書通りの納品だけでは足りず、“+αの提案”ができる企業の方が有利なのです。
「自由提案型」の案件が増えている
近年の入札では、業務内容が完全に固まっていない「自由提案型」や「公募型プロポーザル」といった形式も増えてきています。
これらの案件では、
- 提案の構成や内容に自由度がある
- 技術点や企画性が大きな評価項目になる
- 単なる金額勝負では選ばれない
という特徴があり、企業側には“提案の中で自ら価値を示す力”が問われます。
価格競争から脱したい企業と行政の利害が一致している
行政にとっても「安いけど微妙な業者」に頼むより、適正な価格で良質な提案をしてくれる業者に依頼したいのが本音です。
一方、企業にとっても「価格勝負は消耗戦」だと感じているケースが多く、価格以外の軸で評価される土壌が整いつつあります。
こうした背景から、「提案力」は今後さらに重要性を増していくと考えられます。
このように、提案力はただの“書類づくりのスキル”ではなく、発注者と事業者をつなぐ信頼の設計図とも言えます。
入札で勝てる提案書の共通点とは?
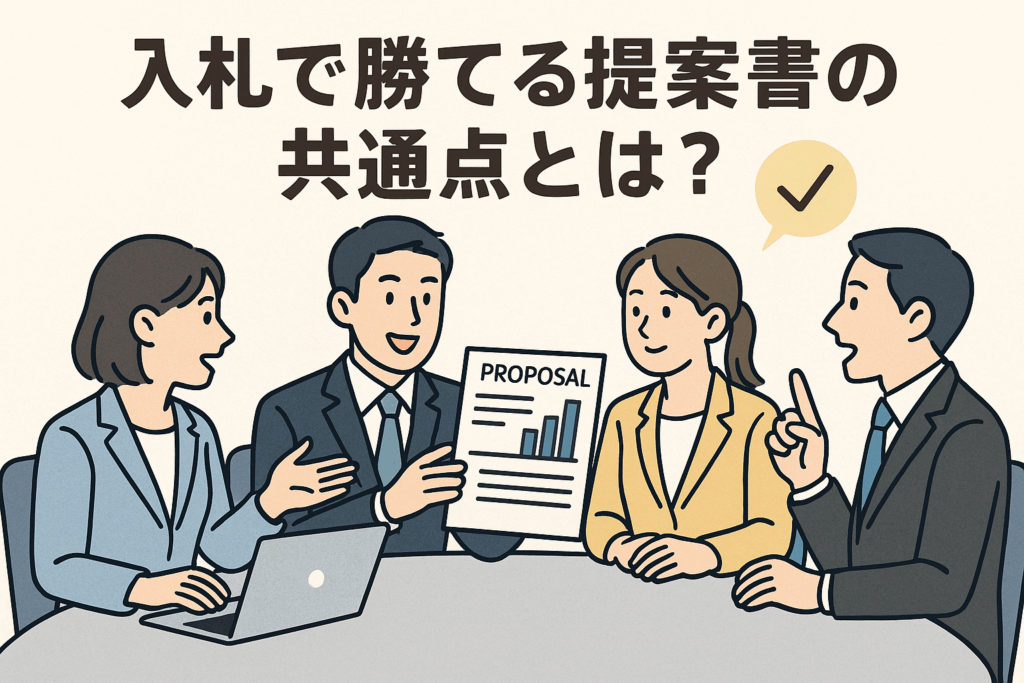
「何を書けば通るのかわからない」
「どこまで具体的に書けばいいのか悩む」
——提案書づくりにおける悩みは、どの企業も共通です。
しかし、実際に入札で選ばれている提案書には、いくつかの明確な共通点があります。
ここでは、審査側が「この企業に任せたい」と感じる提案書の特徴を解説します。
読み手(行政職員)の視点を理解している
入札の審査を行うのは、必ずしもその分野の専門家とは限りません。
多くの場合、発注業務を担当する行政職員が評価するため、以下のような視点が求められます:
- 「市民からの問い合わせに対応しやすいか?」
- 「実現可能性が高いか?過去に似た実績があるか?」
- 「内部稟議(りんぎ)が通りやすい内容になっているか?」
つまり、提案内容が「自分たちの言葉に置き換えやすいかどうか」が評価ポイントの一つになるのです。
“どう実現するか”までを丁寧に書いている
提案書でよくあるNGが、「やります」「できます」といった抽象的な表現で終わっていることです。
信頼される提案には、必ず“実現手順”が具体的に書かれています。
例:
- ✕「SNSでPRを行います」
- ◎「公式アカウントを開設し、月4本の投稿を行います。ネタ出し→画像作成→投稿→数値分析の体制は下記の通りです」
このように、「実施フローと担当体制」を具体的に書くことで、審査側に安心感を与えられます。
見た目・構成にも気を配っている
内容が良くても、読みづらいレイアウトや文字だらけの資料では伝わりにくくなります。
評価されやすい提案書は以下のような構成を意識しています:
- 見出しや段落が整理されており、1ページあたりの情報量が適切
- キービジュアルや表・図解を活用し、視覚的にわかりやすい
- ページごとに「このページでは何を伝えるか」が明確
とくに自治体の案件では、“資料として住民にも共有される可能性”があるため、見やすさは重要な加点ポイントになります。
提案の先にある“成果”が見えている
行政が本当に求めているのは、「作業」ではなく「成果」です。
評価される提案書には、以下のような“成果のイメージ”が盛り込まれています:
- 明確なKPI(例:閲覧数○○件、参加者○○人)
- 住民・利用者の声をどう拾い、どう活かすか
- 長期的な運用体制への配慮
単に業務を遂行するだけでなく、“なぜこの取り組みが地域に必要なのか”を言語化できているかどうかが問われます。
現場で実践されている“提案力の磨き方”
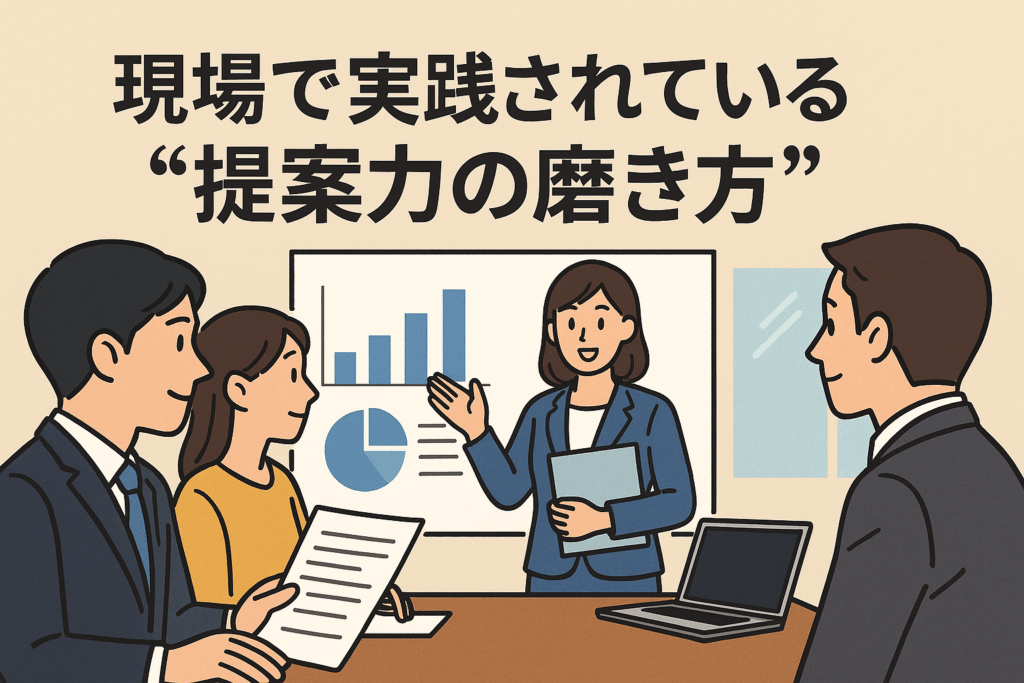
提案力は、一朝一夕で身につくスキルではありません。
しかし、日々の積み重ねや体制の整備次第で、着実に育てていくことができます。
ここでは、実際に入札で成果を出している企業が実践している「提案力を磨く取り組み」を紹介します。
過去の仕様書・提案書を“資産”として蓄積する
過去に参加した案件の仕様書や提案書は、提案力の宝庫です。
内容を蓄積し、案件ごとの成功・失敗パターンを整理することで、次回以降の提案が圧倒的に効率化されます。
- 提案書のフォーマットや構成例を社内共有
- 仕様書と評価結果のセットで振り返る
- “通った提案”と“落ちた提案”の違いを分析
ナレッジ化が進めば、属人化の防止にもつながり、チームとしての底力も上がります。
行政の課題や目的を深掘りする“リサーチ力”を養う
良い提案は、「仕様書に書かれていないニーズ」まで読み取ることで生まれます。
そのために重要なのが、普段からの情報収集とリサーチ習慣です。
- 過去の議会資料や行政方針をチェックする
- 住民の声が出ているSNS・地域メディアを見る
- 同様の取り組みをしている他自治体の事例を調べる
こうした情報があるだけで、提案の説得力が一段と増します。
チームで提案をつくる体制を意識する
提案書を一人の担当者に任せきりにすると、視野が狭くなり、内容が薄くなる傾向があります。
受注率の高い企業では、提案づくりをチームで行い、以下のような仕組みを構築しています:
- 担当:構成・ライティング
- 担当:デザイン・図解
- 担当:チェック・ブラッシュアップ
- 上司による最終レビュー・差別化の提案
複数人でレビューを重ねることで、抜け漏れのない、読みやすく納得感のある提案書が仕上がります。
「提案スキル」は業務の一部として育てていく
提案力は、一部の営業担当だけが持っていればいいスキルではありません。
業務全体に関わる力であり、社内で“学習・共有・改善”の文化をつくることが、提案力を底上げする近道です。
- 勉強会や事例共有会を定期的に実施する
- 他社事例を取り入れてアップデートする
- 外部アドバイザーやパートナーにレビューを依頼するのも有効
小さな案件でも「提案力を試す場」として位置づけることで、会社全体が“提案に強い体質”になっていきます。
まとめ:提案力は一朝一夕では身につかない。だからこそ“積み重ね”が武器になる
入札で選ばれるために必要なのは、単なる「安さ」ではありません。
今の時代、発注者が求めているのは、業務を超えて“成果”を生み出してくれるパートナーです。
その信頼を獲得するカギこそが、提案力です。
提案力とは、以下のような力の総合体です:
- 課題を正しく読み解く力
- 相手のニーズに寄り添う想像力
- 自社の強みを言語化する伝達力
- 書類を通じて信頼を届ける表現力
これらは、一回の入札で身につくものではありません。
1件1件の入札に真剣に向き合い、仮説と振り返りを積み重ねることで、少しずつ“武器”になっていきます。
提案書が選ばれなかったときこそ学びのチャンスです。
“落ちた理由”を考え、次の提案にどう活かすか。
このサイクルを回し続けた企業こそが、価格競争に振り回されない強さを手にしていきます。
価格に頼らず、提案で選ばれる企業になる。
その第一歩は、「ただ書く」から「伝える」に切り替える意識かもしれません。
次の入札案件で、あなたの提案が選ばれることを願っています。